■パラディソ1級インストラクター
インストラクターに憧れ46歳でパラディソのインストラクターになって丸1年。
自営業と週3パートと3人の子育てと養成講座で体調を崩し、インストラクターを諦めようと思っていた所、はーなの「自分の体の為にやりなさい」という言葉にパラディソ体操を習得する事は自分の体にも良いと思考を変える事が出来ました。今も更年期やその他諸々の不調を治せずにいますが、念願のインストラクターをしもじクリニック様で担当させて頂き、会員様と共に楽しく体操しております。
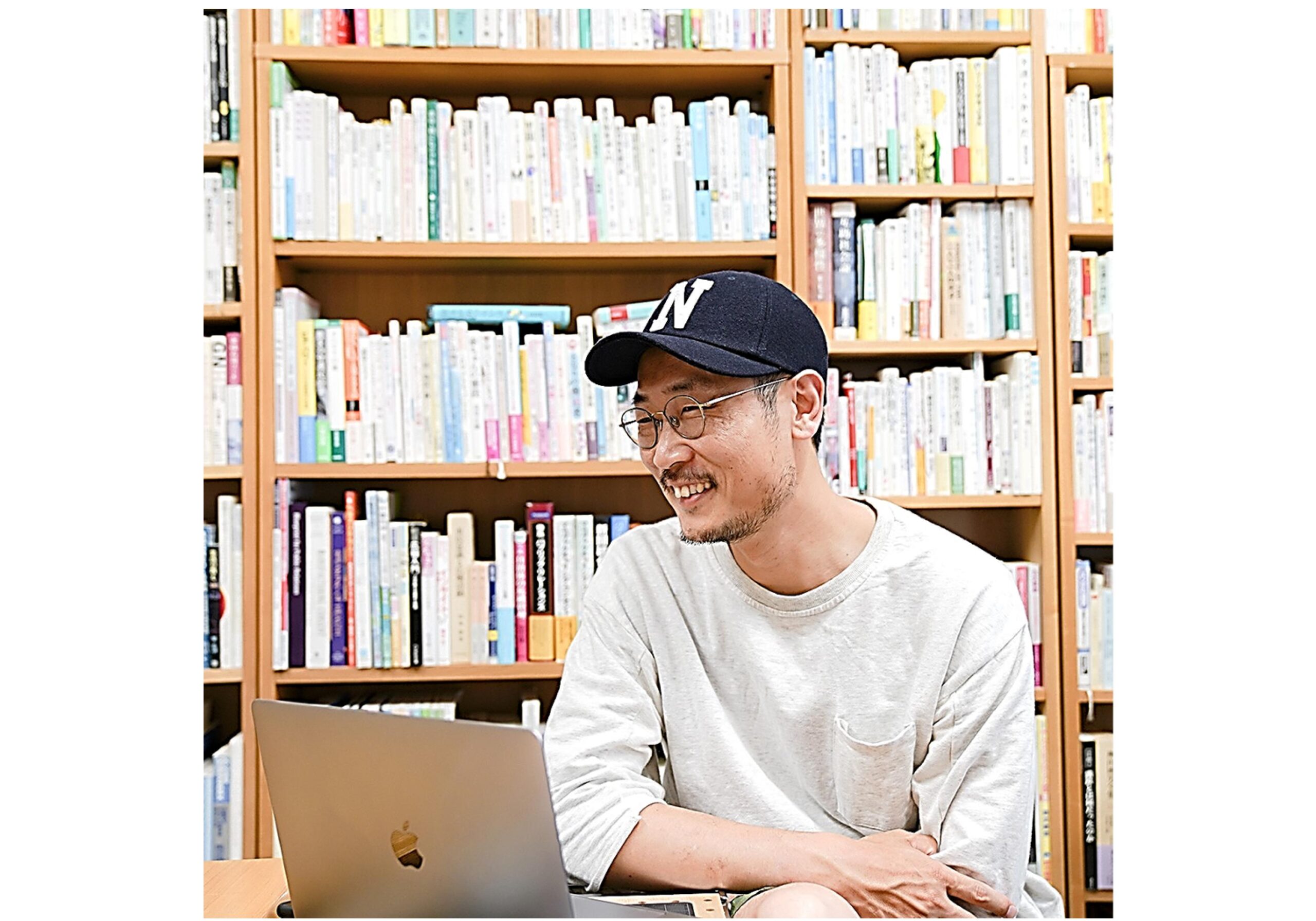
「市民の言葉」として多様な意味を有する「まちづくり」は、まずは、相手がどのような意味で用いているかを理解することが肝要です。今回は、学生が市役所の職員とやりとりしたケースから「まちづくり」の捉え方を深めてみたいと思います。
【例1】A市の「まちづくり協議会」を調査したくて「まちづくり推進課」に連絡したら「コミュニティ推進課」が窓口だと教えてもらった。
もうひとつ、似たような例を見てみましょう。
【例2】B市の「協働推進課」の方に町内会の課題を尋ねたら「まちづくりは『地域コミュニティ課』が担当なので、確認してみます」と言われた。
2つのケースとも行政の職員の方であれば腑に落ちるかもしれません。しかし、学生にとっては謎です。
まず、【例1】の「まちづくり推進課」は、土地区画整理事業や地区計画などを担当している部署でした。「都市建設部」の中の「まちづくり推進課」だったんですね。前回「まちづくり」はそもそも都市計画の分野から拡がった言葉であると紹介しました。その文脈からの「まちづくり」です。大学の研究者でも「まちづくり」を教えている方は、都市計画・開発、公共インフラの整備を専門としている場合が多いです。ディシプリンには学術的な安定性が求められますから、「まちづくり」の現場での意味が多様であったとしても、そういう傾向が強くなるのです。
【例2】は、さらに分かりにくいかもしれません。協働推進課は、市民活動やNPOとの協働、中間支援等を担当しています。ここでは、こうした営みを「市民団体活動」としておきましょう。「市民団体活動」と「町内会や自治会等の活動(地縁団体活動、としましょう)」が別の部署に分かれていて、かつ、後者を「まちづくり」と呼び慣わしているケースです。こうした背景について、さらに深めてみます。
2つのケースに共通しているのは「コミュニティ」という言葉です。国内で「コミュニティ」の施策が推進され始めた時代は「まちづくり」が使われ始めた時代と重なっています。つまり、特に「行政」においては「コミュニティ」の活動が概ね「まちづくり」と解される根拠のひとつが、その時代性にもあります。
「コミュニティ」が国(旧自治省)の施策として提唱されたのは、1969年です。経済優先の国土づくりの結果生じた地域課題に対応すべく、従来から農村部に根付いていた「村落共同体」や都市部に見られた「町内会」等の伝統的な地縁団体と異なる「市民としての自主性と責任を自覚した個人および家庭を構成主体として、開放的でしかも構成員相互に信頼感のある集団」[1]として「コミュニティ」づくりが目指されました。
ちなみに「町内会」等は戦前から存在していましたが、戦時中は行政の末端組織として、国家による戦時宣伝(プロパガンダ)を担いました。その結果、戦後、GHQにより結成が禁じられます。しかし、1952年のサンフランシスコ講和条約にてこの政令は失効し、再び「町内会」等が復活することになります。その際、戦時の反省から、行政との分離が図られ、自主的な自治組織としての運営が目指されました。しかし実質的には、行政の末端・補助的機能を併せ持った組織として現在に至ります。
1969年から展開した「コミュニティ」施策は、1980年代まで活発に続きます。バブル景気にも背中を押され、コミュニティ・センター等のハード整備に一定の成果を残します。しかし、当初目指された「町内会」等に代わる新たな「コミュニティ」が形づくられたかというと、そうでもありません。実質的には、高度経済成長期を経て弱体化した「町内会」等の地縁団体が「コミュニティ」として再編され、地域の「まちづくり主体」として位置付けられたケースが少なくありません。一般的に行政での「コミュニティ推進課」や「地域コミュニティ課」等の部署は、この時期から続く「コミュニティ」施策を下敷きにしています。「まちづくり」という言葉が醸し出す行政の関与と地縁のイメージには、こうした意味合いもあるのです。
さて、1990年代前半にはバブルが崩壊します。国や自治体の財政が厳しくなる中で、コミュニティ施策もシュリンクしていき、コミュニティ組織の形骸化が見られる一方で「コミュニティ」の役割が、より一層必要な時代となります。そんな中、阪神淡路大震災(1995年)により、地縁を越えたボランティアの意義が見出され、NPO法(1998年)の制定に結実し、「市民団体活動」が拡がっていきます。その後「まちづくり協議会」等により、こうした「市民活動団体」の取り込みが目指されますが、【例2】のように「市民活動団体」と「地縁活動団体」との区別が維持されているケースがほとんどです。
また、時を同じくしたエポックメイキングな出来事と言えば、インターネットです。インターネットの拡がりは「コミュニティ」にも大きな影響を与えます。従来までは、地縁に関係なく関心でつながる機能的な人間関係は「アソシエーション」あるいは「テーマコミュニティ」と称され、地縁を前提とした「コミュニティ」と区別されていました。しかし、2000年始めくらいからインターネット上で「コミュニティ」という呼称が拡がっていきます。そうした傾向を踏まえ、従来からの「コミュニティ」は、冒頭に「地域」と付して、現代では「地域コミュニティ」と称されるようになりました。 現代における「まちづくり」そして「コミュニティ」の意味は、その後の「新しい公共」や「まちづくり三法」、「地方創生」の展開等にも影響を受けますが、そのあたりは、次回にお話しましょう。
[1] 国民生活審議会調査部会(1969)「コミュニティ〜生活の場における人間性の回復〜」

九州大学 専任講師
福祉とデザイン 理事
社会福祉士
田北雅裕 TAKITA Masahiro

■パラディソ1級インストラクター、10分ランチフィットネス®教育トレーナー
皆さまいかがお過ごしでしょうか?現在、高宮にある大田クリニック様の2階で月、水、金とパラディソ体操が開催されています。私は月曜日に担当しております。
60代〜80代のクリニック患者様やご近所で知人から聞いて参加、という方もいらっしゃっています。体操の準備をしながら皆さまの近況を伺うのが楽しみで、その日の体調などでメニューを調整することも!
有酸素はステップ台に変えて10分ほど踏み、脳トレやレクの要素を取り入れながら会話あり笑いあり。コロナ禍なので気をつける点を守りながらワイワイと行っています。
「参加者の元気な声が響いてほしい!」
それは始めに院長先生からのご要望でもありました。その賑やかな声に誘われてまた新しい仲間が増えると嬉しいな〜と思います。
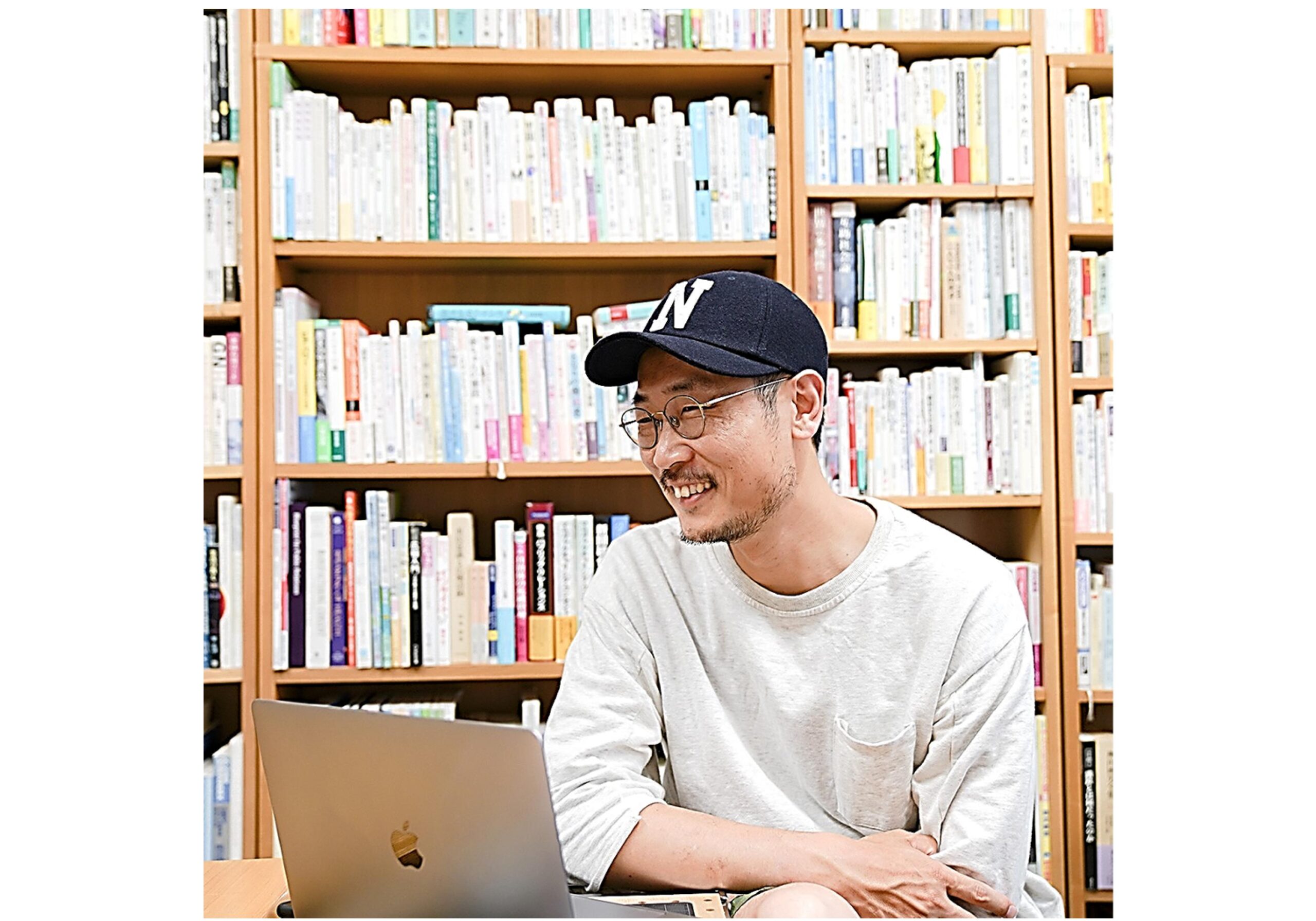
「まちづくり」という言葉は、雑誌「都市問題(1952)」で歴史学者の増田四郎が「町つくり」と記したことが初出と言われています。60年代に入り、近代都市計画に対する反省が世界的になされていく中で、従来の官主導のトップダウンの都市計画手法ではなく、ボトムアップの自治形成、および市民が主体的に関わる計画づくりが目指されていきます。そうして70年代に、革新自治体を中心に「都市計画」に代わる言葉として「まちづくり」が使われ始め、市井に広がっていきました。
一方で、都市計画における市民へのまなざしは、戦前にすでに見られていました。例えば、都市美運動を牽引した橡内 [1] は、1927年9月の岩手日報で「国の定める『都市計画法』を適用しさえすれば必ず合理的な優良な都市が実現するものと思うのは早計に失する。…やはり、市民諸君の愛市心にまち、真に自己の住む町をよいものにしたいという誠意から、常に世論の形をもって、実行機関を把握しておる当局を鞭撻し、当局もよく市民の声を聴き、あまねく衆知をいれて、一面に欧米都市の進歩せる経営方法を参考とし、他面によく己の都市の民情風土等を斟酌して最も合理的なプランをたてねばならない」と綴っています。さらに、農村における生活改善運動や部落解放運動等、都市計画とは別文脈においてもボトムアップの「まちづくり」に連なる潮流が、確認できます。
そうした流れが70年代以降に「まちづくり」として束ねられていった背景には、戦後の急激な環境変化を経て高度経済成長期を経験した日本において、「公害」に代表されるように、市民の身近な暮らしが蔑ろにされる事態が生じたことが大きく影響しています。世界的にもベトナム戦争の反戦運動等が顕在し、市民が自ら声を上げる機運を後押ししていきます。また、地域開発のあり方に疑義を唱えたシューマッハーが「Small Is Beautiful(1973)」を著したのもこの時期です。氏が提唱した「内発的発展」や「地域主義」に連なる思想は、過疎地の活性化を目指した「村おこし」等にも強い影響を与えます。都市部においては、旧来の町内会等に代わる小学校区を単位とした「コミュニティづくり」が模索されていき、そうした制度や運動に背中を押されるかたちで「まちづくり」の概念が形づくられていきました。
その後「まちづくり」は、さらに多様な様相を帯び、結果的に現在は、都市計画分野だけでなく、保健医療・福祉・観光等、市民の暮らしに関わる全ての領域を包含し、多主体で協働しながら身近な暮らしの課題を改善していく概念として用いられています。平仮名による「まちづくり」は、海外で Machizukuri と称されるように、多様な解釈を促しながら日本独自の概念として昇華しました。今となっては定義すら困難である「まちづくり」は、その解釈が市民に委ねられているという意味において、まさに「市民の言葉」として生き続けていると言えるでしょう。
[1] 中島直人他(2001)「都市美運動家・橡内吉胤に関する研究」都市計画論文集Vol.36
参考:日本建築学会(2004)「まちづくりの方法」丸善株式会社

九州大学 専任講師
福祉とデザイン 理事
社会福祉士
田北雅裕 TAKITA Masahiro

■パラディソ1級インストラクター&10分ランチフィットネス®教育トレーナー
皆さま、ご無沙汰しております。いかがお過ごしですか?
私は現在、しもじ内科クリニック様に併設されているメディカルフィットネス nico nico studioにて、火曜日のパラディソ体操2を担当しております(今年4月のIRクラブ通信「パラディソ 出張先レッスンの様子」でもご紹介いただきました)。
レッスンに参加されるのは、全員クリニックの患者様ですが、50〜80代の明るく元気な方々です。クリニックHPのレッスン紹介には「素敵に歳を重ねるクラス」とあります。
スタジオ名の由来にもなっているニコニコペースを大切に、素敵に歳を重ねるためには…を模索しながら地道に活動しております。
プライベートでは、思春期の入口付近にいる あまのじゃくな長男(小5)と、泣き虫だけど負けず嫌いな次男(小1)の育児に奮闘?しております。

■パラディソ1級インストラクター
皆さま、大変ご無沙汰しております。私は、埼玉県にて3歳のおませな娘、5歳のアクティブな息子の子育てに奮闘中です。最近の大きな出来事は、4月に娘が幼稚園に入園したことです。
コロナ禍で、市の子育て支援による公共施設での幼児の催しやサークル活動、プレ幼稚園…と、大半が休止となりました。同じ年の子ども達との触れ合いが極端に少なく「お母さんベッタリ」だった娘。幼稚園での時間を心配していましたが…
母の心配はどこ吹く風(>_<)登園初日から、手を振る母を振り返りもせず、先頭きって登園しました!
いつの間にか、成長していく娘に嬉しい驚きの毎日です。とはい、まだまだ3歳。
年長組にいるお兄ちゃんに、心細くなる度に抱っこぎゅっ!」して背中をトントンしてもらっているようです。息子曰く、僕が「お兄ちゃんがいるよ、大丈夫大丈夫だよー」って言うと魔法みたいに元気になれるんだよ!とのこと。
優しい気持ちで、自分の事以上に妹を思いやれるようになった息子の成長にもたくさんパワーをもらっています。これからも、子どもの成長が楽しみです☆

■パラディソ1級インストラクター
私は、日ごろ健康運動指導士として公民館等で運動指導をしています。
そこで、コロナ禍でとても苦労していることが1つあります。それがマスクで、参加者の表情が全く分からない事です。具合が悪いのか?元気なのか?余裕なのか?きついのか?など今まで顔の表情で把握できていたことが全くできなくなりました。
そこで、解決法として、『元気ですか→挙手』ではなく、レクの要素をとり入れ、体調チェックのポーズを毎回変えながら確認することに。「あら??何だったかな?そうだ、元気だから右足上げるんだ」とか場が和むのと、認知症予防につながると好評です。
ところで、娘が小学生になりました。今までは育児でバタバタして自分を振り返る時間がありませんでした。人生初めての腰痛になり、自分のメンテナンスが必要だと感じるようになりました〜。身体が元気になると何だか気持ちもウキウキしてきますよね。あ〜春よ来い‥

在宅勤務は、働き方だけでなく、生活習慣やメンタルヘルスにも大きな影響を与えます。このことは、特に、在宅勤務を希望するかどうかで、大きく違ってきます。第1回目で紹介したように、新型コロナウイルス流行以前は、在宅勤務は、希望する人が好んで選択する働き方の一つでした。しかしながら、新型コロナウイルス流行下では、労働者の希望とは関係なく、社会的要請として在宅勤務が導入されました。その結果、在宅勤務をしたくないのに、在宅勤務をせざるを得ない、ミスマッチという問題が発生しました。これは、これまでになかった問題です。
在宅勤務は、対人コミュニケーションの機会を減らすことや、上司、同僚などの職場からの支援を得られにくいことが指摘されています。また、在宅勤務になると、通勤を通じて当たり前のようにしていた外出や、通勤途中でちょっとした買い物や食事をするという楽しみの機会も減ります。その結果、在宅勤務の頻度が増えるほど、メンタルヘルスに悪影響があるのではとの懸念があります。
ところが、ミスマッチに着目して在宅勤務とメンタルヘルスの影響を分析してみると、面白い関係がわかりました。在宅勤務をしたい人は、在宅勤務の頻度が多いほど、メンタルヘルスの状況が良くなっていました。逆に、在宅勤務をしたくない人は、在宅勤務の頻度が増えるほど、メンタルヘルスに問題を抱える人が増加していました。当たり前の事のように思うかもしれませんが、このようにミスマッチによって、働き方のスタイルが健康に異なる影響を与えるということは、とても重要なことです。
このような問題は、在宅勤務に限らず、これまでもお仕事のスタイルの中には多くあります。その典型は、交代勤務や夜勤です。交代勤務や夜勤という働き方も、そのような働き方が合う人と合わない人で、健康影響が異なることがわかっています。したがって、このような場合は、本人の適正、希望を考慮した適正配置という考え方が必要になります。今後、新型コロナウイルス流行が落ち着いてきても、在宅勤務という働き方は、どんどん普及すると言われています。在宅勤務のミスマッチをどのように調整していくかは新しい課題と言えます。
最後に、在宅勤務における食生活の影響について紹介します。在宅勤務をしている人では、在宅勤務をしていない人に比べて、以下のような不適切な食生活になりやすいことが報告されています。
特に、一人暮らしの場合、在宅勤務による食習慣の影響を受けやすいことがわかっています。
在宅勤務をする際には、仕事をする際の作業環境だけでなく、食生活にも気を付けるようにしましょう。
Otsuka, S., et al. A Cross-Sectional Study of the Mismatch Between Telecommuting Preference and Frequency Associated With Psychological Distress Among Japanese Workers in the COVID-19 Pandemic. Journal of Occupational and Environmental Medicine (2021) Kubo, Y., et al. A cross-sectional study of the association between frequency of telecommuting and unhealthy dietary habits among Japanese workers during the COVID-19 pandemic. Journal of Occupational Health (2021)
産業医科大学 産業生態科学研究所 環境疫学研究室 教授
藤野 善久
一般社団法人10分ランチフィットネス協会
(スタディオパラディソ内)
| 住所 | 〒815-0071 福岡県福岡市南区平和1丁目 2番23号(スタディオパラディソ内) |
|---|---|
| 電話番号 | 092-524-2245 |
| Fax番号 | 092-524-2281 |
●電話受付時間/9:00~18:00(土・日・祭日休み)
●西鉄バス「山荘通りバス停」より徒歩1分
●西鉄大牟田線「平尾駅」より徒歩5分
●お客さま駐車場はございません。近くのコインPをご利用願います。