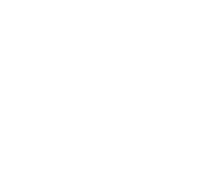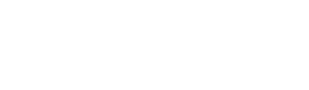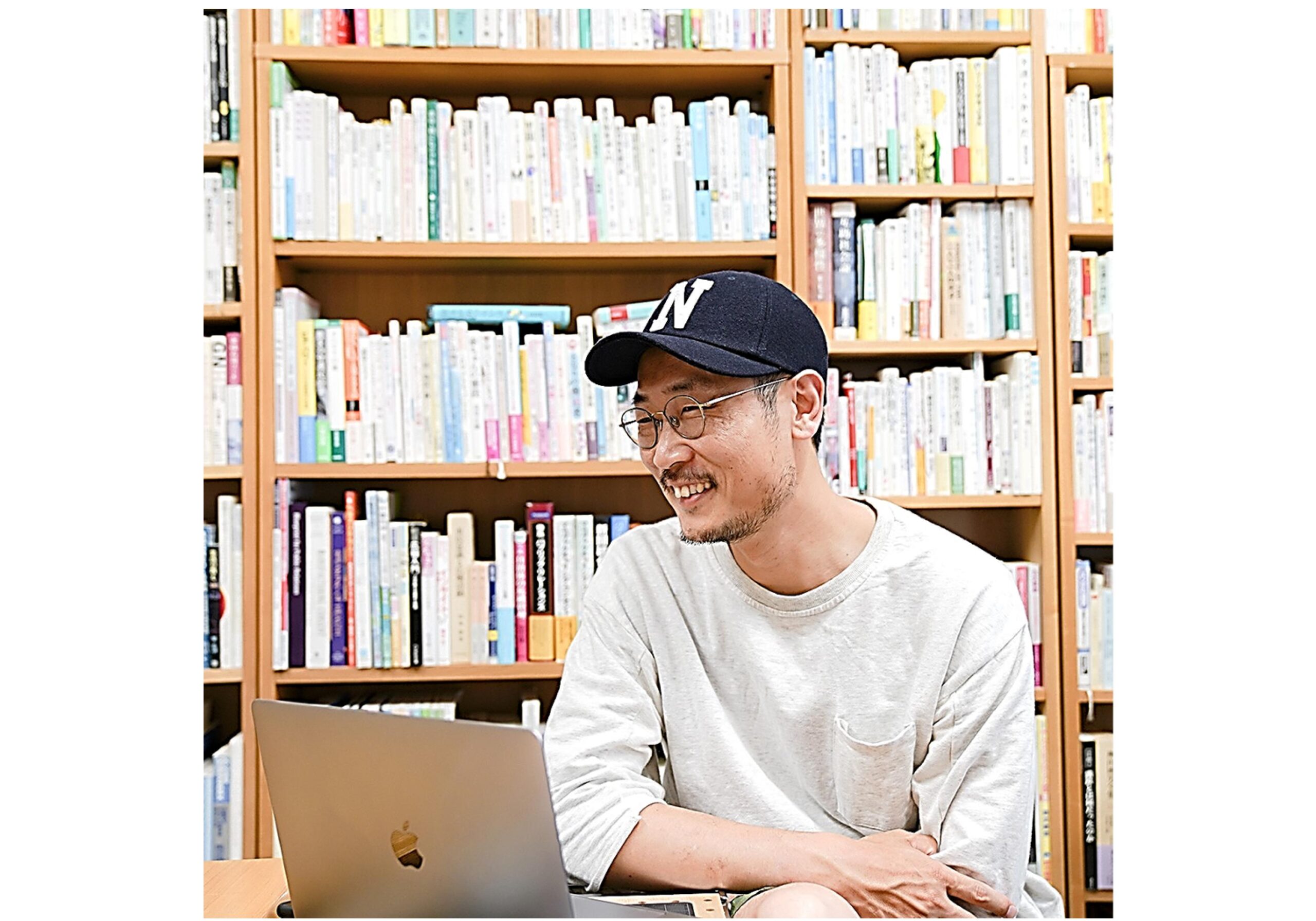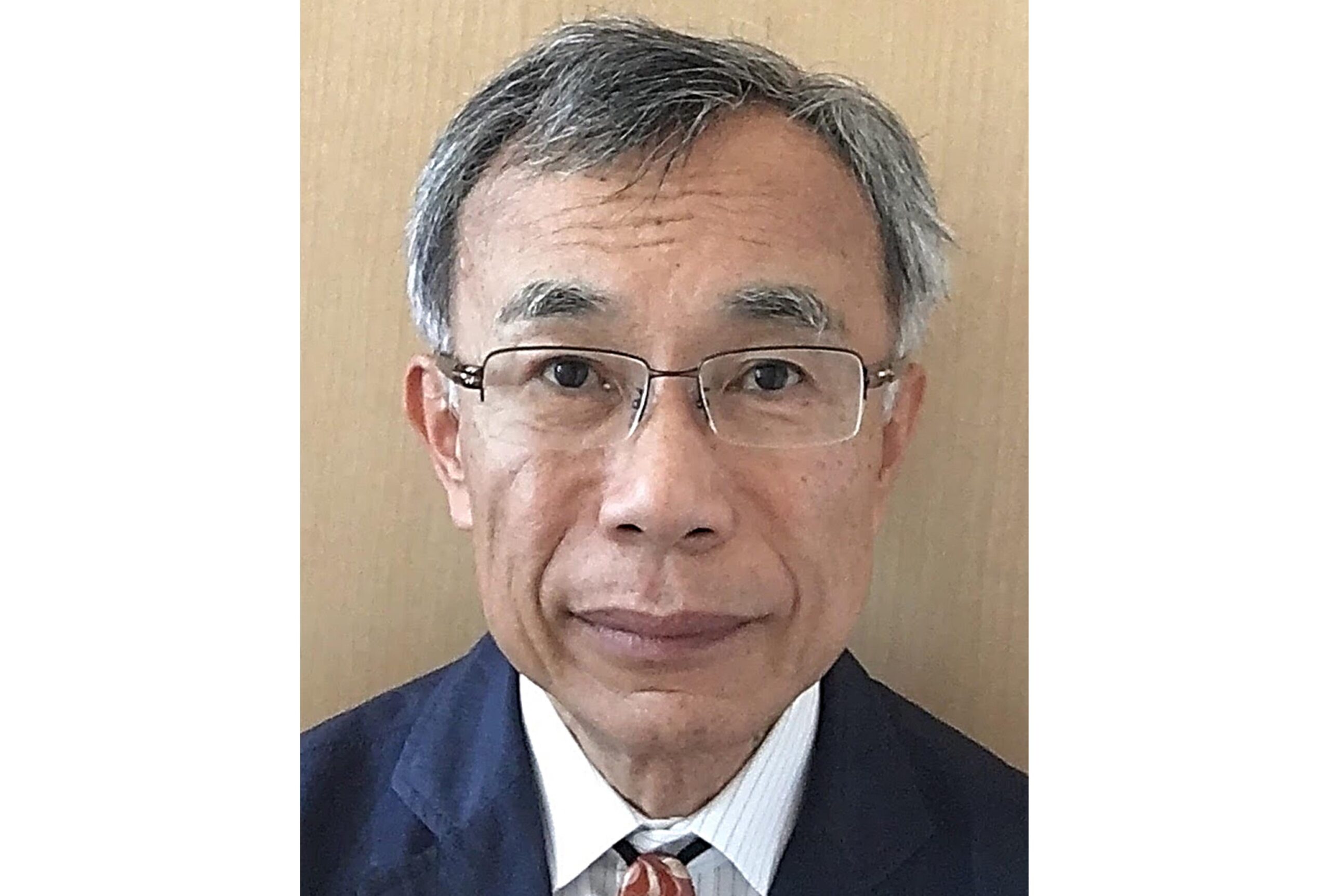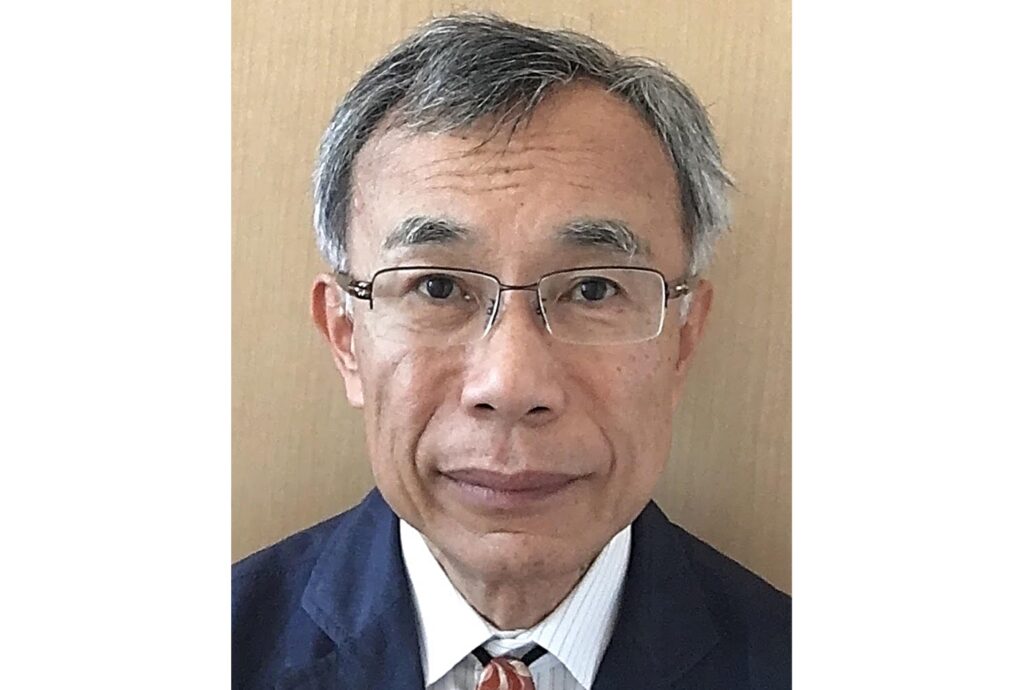「まちづくり」の近年の傾向として、地域経済の振興(狭義の地域活性化)が強調される機会が増えてきました。60年代の高度経済成長期を経て生じた地域格差からその傾向が強化されていくわけですが、詳細は市川氏の論考(2001) [1] に整理されていますので、関心のある方は読んでみてください。この2001年以降は、さらなる人口減少社会を迎え、第二次安倍内閣により推進された「地方創生」が競争の論理を肉付けし、分かりやすい政策で言うと「ふるさと納税」も、結果的に自治体間の表層的な競争を促してきた(促すことになってしまった)と言えるでしょう。
一方で、「まちづくり」に地域経済の振興が含意するに至った理由は、市川氏が指摘する文脈だけではありません。例えばそのひとつは「中心市街地のまちづくり」です。職住分離が進んだ1970年代以降、中心市街地の空洞化が進み、商店街の活性化等が模索されていきます。そして1998年に「中心市街地活性化法」が制定され、関連法である「大店立地法」「都市計画法」を含めた3つの法律は、地域に応じた一体的な「まちづくり」に取り組むことを趣旨として「まちづくり三法」と称されることになります。その結果、多様な意味を含むはずの「まちづくり」の「まち」が、中心市街地および都心部に最適化された「街(まち)」を前提に語られる場面が増えてきました。自治体の財政難は、バブル崩壊やリーマンショック等の社会背景が導いた面も確かにありますが、想定可能な人口減少社会への備えを怠り、バブル期のバイアスを引きずりながら正当化してきた、読みの甘い公共事業の反動が大きく影響しています。そうした従来までの(中心市街地に限らない)「まち」の事業マネジメントのオルタナティブを求める姿勢が「街」の論理を拡大させている面もあるのでしょう。一方で「まちづくり」に経営的観点が不可欠なのは自明です。その上で、現場の眼差しをアップデートする必要を感じています。なぜなら、特に現場レベルにおいて、解像度の低い経営概念に市民の存在価値が見過ごされる局面を散見するからです(例えば単純な受益者負担のサービス構造のみが想定され、生活保護をはじめとした公的扶助の意義が共有されないような)。では、これからの「まちづくり」のヒントはどこにあるのでしょう?幾つかの視点はありますが、今回はそのひとつ、「コミュニティ・デザイン」から見出してみましょう。
近年広がりを見せてきたコミュニティ・デザインの一般的な理解は、Artwords[2]で書かれている内容に沿っている気はします。より正確には、2010年にリノベーションされたマルヤガーデンズ(鹿児島市)での仕事において、山崎氏が「コミュニティ・デザイン」という言葉を用い、今まで取り組んでこられた実践を文脈化し、提起されたことで広がっていったと僕は記憶しています。一方で、ここには触れられていないコミュニティ・デザインの系譜がありますので、今回はそこに着目してみます。
例えば僕の手元には、1976年に発行された建築雑誌「建築文化 Vol.31」があります。その特集は「コミュニティ・デザイン」です。また、1977年に発行された建築雑誌「PROCESS: Architecture No.3(以下、P.A)」もあります。この特集も「住民参加のコミュニティ・デザイン」です。つまり、前回のコラムで触れた「コミュニティ」が国内に広がる1969年以降に「デザイン」と結びついた概念提起が、1970年代にすでに見られます。ちなみに「建築文化」の「コミュニティ」は、一定の地理的範囲にある居住環境を指し、「デザイン」は物的環境の整備を指す狭義の概念として用いられています。宅地よりも広いスケールの居住環境に対して「コミュニティ」を重ねたものであり、こうした意味付けは前回コラムで紹介した「コミュニティ」に通じる定義であり、建築•都市計画分野では現代でも見られるベーシックな用法です。
一方、P.A.は、アメリカで60年代から実践されてきたコミュニティ・デザインの特集です。編集を担当した張清獄氏は「デザイン・プロセスの正しい意味、これは建築家やデザイナーの間で常に誤って受け取られている。彼らは自己流にそれを解釈し、『個人的』アプローチということでそれを正当化することが多い。正しい意味のデザイン・プロセスを少しでも理解するために、この特集号ではコミュニティ全体がデザイナーとしてデザイン・プロセスに参加した例を扱っている」とし、さらに建築家であり、アメリカの第3代大統領であるトーマス・ジェファーソンの以下の言葉を引用しています。「社会の最終的な権力、その安全な保管場所としては、大衆以外に私は知らない。もし、大衆が健全な判断力をもって自分たちの力を行使できるほどに啓蒙されていないと思われるなら、その救済方法は大衆の判断力をとりあげてしまうことではなく、彼らの判断力を生かすことである」。45年前に示されたこうした問題提起を、新鮮に感じる人は少なくないはずです。
1960年前後のアメリカの都市開発は、所得や人種に纏わる差別を含んだものでした。そのアンチテーゼとして、アメリカの都市プランナー:ポール・ダヴィドフらにより「アドボカシー・プランニング」が提唱されます。低所得者層等のマイノリティーの声を聴き(つまり、社会的弱者の意見表明の権利を保障し)、そこを起点にコミュニティと共にかたちづくるプランニングです。そのアドボカシー・プランニングを基調にして展開したデザイン手法こそが、コミュニティ・デザインです。そしてその展開は、日本において「まちづくり」が提起された時期と時を同じくします。本記事は字数が限られていますので、詳細を知りたい方は、ランドルフ・T. ヘスター、土肥 真人(1997)「まちづくりの方法と技術―コミュニティー・デザイン・プライマー」をおすすめします。その表紙には「『公正な世界を創りたいと望んでいる人々』に国境はない」「『まちづくり』に関わろうとする人を励まし、勇気づける本」とあります。つまり、エンパワメントを基調にした「ソーシャル・ワーク(あるいはコミュニティ・オーガニゼーション)」と近しい概念であることに、気づいた人もいるのではないでしょうか。
「まちづくり」は、本書が書かれた90年代には想像できなかった程、オンライン・コミュニティの浸透と併せて、保健医療や福祉、アート等、市民の暮らしに関わる全ての領域を包摂する概念として用いられています。また、今回は書ききれませんでしたが、70年〜80年代のアメリカにおいて、アドボカシー・プランニングや市民参加が大きく後退していく局面もあります。しかし、多様な様相を帯びている現代だからこそ、コミュニティ・デザイン、ひいては「まちづくり」が目指してきた「コミュニティと共に公正な世界を創る」プリミティブな姿勢を改めて参照することに意味はあるはずです。その上で、現代に蓄積されてきた連帯と共生の叡智を重ねたい、そう思うのです。
[1] 市川虎彦(2001)「まちづくり論の陥穽 : 地域自立の論理から自治体間競争の論理へ」
松山大学論集 13 (1), 157-175
[2] Artwords(アートワード)|コミュニティデザイン:https://artscape.jp/artword/index.php/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3

九州大学 専任講師
福祉とデザイン 理事
社会福祉士
田北雅裕 TAKITA Masahiro