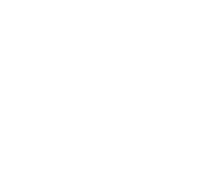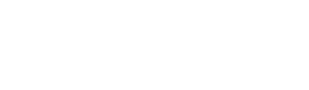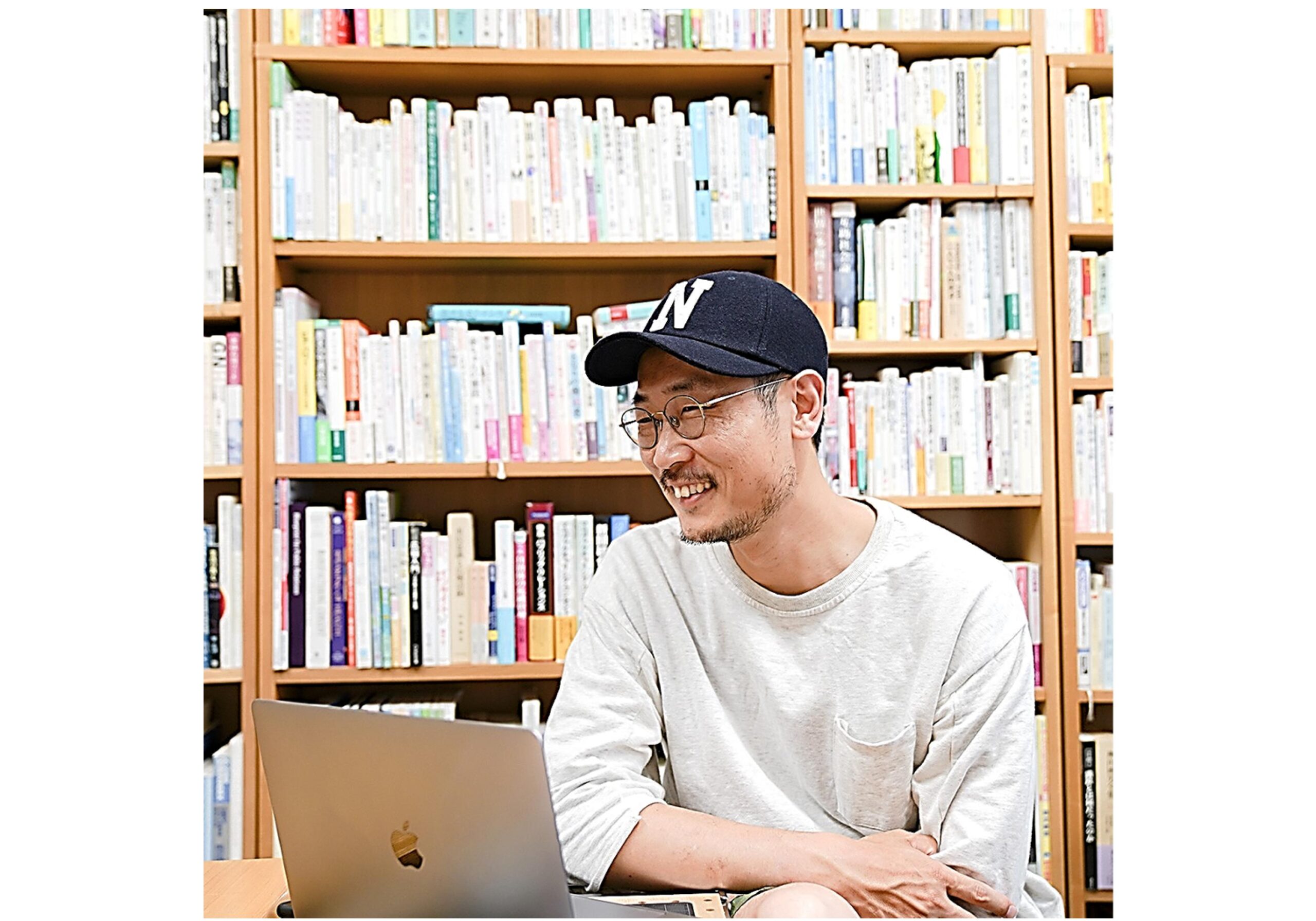在宅勤務は、働き方だけでなく、生活習慣やメンタルヘルスにも大きな影響を与えます。このことは、特に、在宅勤務を希望するかどうかで、大きく違ってきます。第1回目で紹介したように、新型コロナウイルス流行以前は、在宅勤務は、希望する人が好んで選択する働き方の一つでした。しかしながら、新型コロナウイルス流行下では、労働者の希望とは関係なく、社会的要請として在宅勤務が導入されました。その結果、在宅勤務をしたくないのに、在宅勤務をせざるを得ない、ミスマッチという問題が発生しました。これは、これまでになかった問題です。
在宅勤務は、対人コミュニケーションの機会を減らすことや、上司、同僚などの職場からの支援を得られにくいことが指摘されています。また、在宅勤務になると、通勤を通じて当たり前のようにしていた外出や、通勤途中でちょっとした買い物や食事をするという楽しみの機会も減ります。その結果、在宅勤務の頻度が増えるほど、メンタルヘルスに悪影響があるのではとの懸念があります。
ところが、ミスマッチに着目して在宅勤務とメンタルヘルスの影響を分析してみると、面白い関係がわかりました。在宅勤務をしたい人は、在宅勤務の頻度が多いほど、メンタルヘルスの状況が良くなっていました。逆に、在宅勤務をしたくない人は、在宅勤務の頻度が増えるほど、メンタルヘルスに問題を抱える人が増加していました。当たり前の事のように思うかもしれませんが、このようにミスマッチによって、働き方のスタイルが健康に異なる影響を与えるということは、とても重要なことです。
このような問題は、在宅勤務に限らず、これまでもお仕事のスタイルの中には多くあります。その典型は、交代勤務や夜勤です。交代勤務や夜勤という働き方も、そのような働き方が合う人と合わない人で、健康影響が異なることがわかっています。したがって、このような場合は、本人の適正、希望を考慮した適正配置という考え方が必要になります。今後、新型コロナウイルス流行が落ち着いてきても、在宅勤務という働き方は、どんどん普及すると言われています。在宅勤務のミスマッチをどのように調整していくかは新しい課題と言えます。
最後に、在宅勤務における食生活の影響について紹介します。在宅勤務をしている人では、在宅勤務をしていない人に比べて、以下のような不適切な食生活になりやすいことが報告されています。
- ・サプリや菓子パンなど簡単な食事で済ませることが1日のうち2回以上
- ・一日の食事回数が2回以下
- ・一人で食事をすること(孤食)が週に4日以上
- ・朝食を食べないことが週に3日以上
特に、一人暮らしの場合、在宅勤務による食習慣の影響を受けやすいことがわかっています。
在宅勤務をする際には、仕事をする際の作業環境だけでなく、食生活にも気を付けるようにしましょう。
Otsuka, S., et al. A Cross-Sectional Study of the Mismatch Between Telecommuting Preference and Frequency Associated With Psychological Distress Among Japanese Workers in the COVID-19 Pandemic. Journal of Occupational and Environmental Medicine (2021) Kubo, Y., et al. A cross-sectional study of the association between frequency of telecommuting and unhealthy dietary habits among Japanese workers during the COVID-19 pandemic. Journal of Occupational Health (2021)
産業医科大学 産業生態科学研究所 環境疫学研究室 教授
藤野 善久